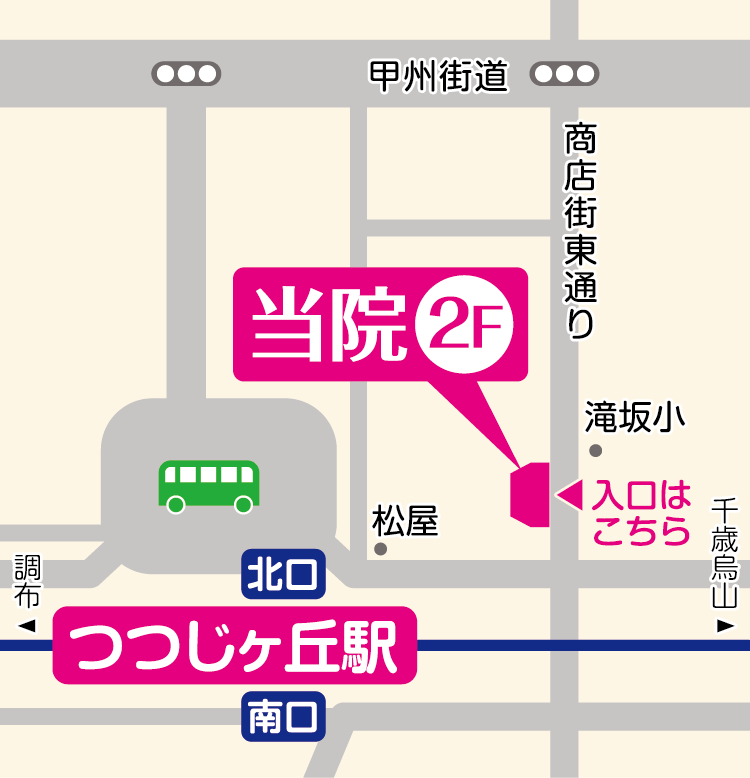女性泌尿器科とは
女性は尿道が短く、膀胱炎をはじめとする尿路感染症になりやすい構造を持っています。さらに妊娠・出産・加齢・更年期などによる骨盤底筋やホルモンの変化が、排尿に関するさまざまなお悩みの原因となります。
「年齢のせい」「女性だから仕方ない」とあきらめてしまう方も少なくありませんが、泌尿器科的な評価と治療により改善できるケースが多くあります。
当院では、女性特有の排尿トラブルや尿検査異常、膀胱・子宮の下垂感や違和感などについて、丁寧な問診・診察・必要な検査を行い、症状や原因に応じて薬物療法・生活指導・骨盤底筋体操などを組み合わせた治療を行います。
このような症状はありませんか?
- 咳やくしゃみで尿が漏れる(腹圧性尿失禁)
- 急にトイレに行きたくなる(尿意切迫)/間に合わない(切迫性尿失禁)
- トイレが近い(頻尿)/夜中に何度も目が覚める(夜間頻尿)
- 排尿時の痛み、にごり、悪臭がある
- 腟から何かが出てきた感じがする(下垂感)
- 健診で「尿に異常がある」と言われた
こうした症状は、過活動膀胱・膀胱炎・腹圧性尿失禁・骨盤臓器脱などの疾患が背景にあることが多く、泌尿器科での評価が必要です。
よくみられる
女性の病気と診療内容
膀胱炎
排尿時の痛み、頻尿、尿のにごり、血尿が典型的な症状です。特に若年〜更年期の女性に多く、急性膀胱炎では尿検査、培養検査で白血球や細菌を確認し、抗菌薬で治療します。
再発を繰り返す場合は、耐性菌・膀胱や腎臓の構造や機能異常・腫瘍や尿路結石・ホルモン変化・排尿習慣など、原因の精査が必要です。
膀胱炎(急性・慢性)
膀胱炎は、膀胱粘膜に炎症が起こる病気で、排尿時の痛み(排尿痛)・頻尿・尿のにごり・血尿が典型的な症状です。ときに下腹部の不快感や残尿感を伴うこともあります。
特に女性は尿道が短く、細菌が膀胱に侵入しやすいため、若年〜更年期の女性に多くみられます。
急性膀胱炎
大半は大腸菌などの細菌感染によるもので、尿検査・尿培養検査で白血球や細菌を確認し、抗菌薬の内服で治療します。十分な水分摂取も大切です。適切に治療すれば数日で改善することが多いですが、症状が残る場合は再検査が必要です。
慢性膀胱炎・再発性膀胱炎
年に2〜3回以上繰り返す場合や、症状が長引く場合には以下のような原因を考えます。
- 耐性菌感染
- 膀胱や腎臓の構造・機能異常(膀胱憩室、残尿過多など)
- 腫瘍、尿路結石の存在
- ホルモン変化(閉経後のエストロゲン低下)
- 排尿習慣や水分摂取量の問題
この場合は、超音波検査・尿細胞診・膀胱鏡・CT検査などで精査します。必要に応じて婦人科などと連携し、原因精査・治療を行います。
再発予防
- 水分摂取を心がけ、排尿回数を減らさない
- 性交後の排尿習慣
- 下半身の保温
- 便秘の改善
受診の目安
排尿時の痛みや頻尿、血尿が出た場合は自己判断で市販薬を使わず、早めの受診をお勧めします。膀胱炎の症状の裏に、腎盂腎炎や膀胱がんなど重大な病気が隠れている場合もあります。
過活動膀胱(OAB:Overactive Bladder)
急な強い尿意(尿意切迫感)、トイレに間に合わない尿漏れ(切迫性尿失禁)、頻尿が主な症状です。日本では40歳以上の約8〜10人に1人が症状を持つとされ、特に中高年以降の女性に多くみられます。日常生活や睡眠に影響し、生活の質(QOL)を大きく低下させます。
過活動膀胱は、膀胱の筋肉(排尿筋)が過剰に収縮することが原因で、原因としては加齢、女性ホルモンの低下、脳や脊髄疾患(脳梗塞、パーキンソン病など)、前立腺肥大症、骨盤底筋の衰えなどがあります。また、明確な原因が特定できない場合も少なくありません。
診断
症状の聞き取り(排尿日誌や質問票)を行い、尿検査や残尿測定、超音波検査で他の病気(膀胱炎、膀胱がん、結石など)がないかを確認します。必要に応じて尿流測定や膀胱鏡検査を行います。
治療
1. 生活指導
- カフェインやアルコール摂取の見直し
- 水分・塩分摂取量の調整
- 就寝前の水分制限
- 便秘の改善
2. 行動療法
- 膀胱訓練(尿意を感じても少し我慢して排尿間隔を延ばす)
- 骨盤底筋体操(特に腹圧性尿失禁を伴う場合)
3. 薬物療法
- 抗コリン薬
- β3作動薬
どちらも膀胱を緩め、尿をためやすくする薬です。副作用や合併症に応じて薬剤を選択します
4. ボトックス膀胱壁注入療法(薬物療法で効果が乏しい場合)
膀胱鏡使用下に膀胱の筋肉にボツリヌス毒素を注入し、過剰な収縮を抑える方法で、数か月間効果が持続します。
受診の目安
「トイレが近い」「急に強い尿意がくる」「夜何度も目が覚める」などの症状が2週間以上続く場合は、放置せずに泌尿器科での評価をお勧めします。早期に治療を始めることで、症状の改善と再発予防が期待できます。
腹圧性尿失禁
咳・くしゃみ・運動など腹圧がかかった時に尿が漏れる状態です。出産歴のある方や中高年女性に多くみられます。
軽症では骨盤底筋体操や薬物療法を行います。
重症例では外科的治療が有効で、必要に応じて専門施設に紹介いたします。
骨盤臓器脱(子宮脱・膀胱瘤)
腟から「何か出てくる感じ」や下垂感、排尿困難などを伴う疾患です。出産歴や加齢、閉経が主な要因です。
治療はペッサリー装着や骨盤底筋訓練を行い、症状が強い場合は手術治療を検討します。必要に応じて、婦人科とも連携して診療します。
尿検査異常(尿潜血・たんぱく尿)
女性の健診でよくみられる所見ですが、膀胱がん・腎疾患・尿路結石・感染症などのサインであることがあります。
当院では超音波検査・尿細胞診・膀胱鏡検査などで原因を特定し、必要に応じて腎臓内科や婦人科と連携します。
恥ずかしい・
相談しづらい症状だからこそ
「尿もれ」「におい」「頻尿」などの症状は、恥ずかしさから受診をためらわれがちですが、泌尿器科的には原因を明らかにし、治療で改善できるケースがほとんどです。
当院では、女性医療スタッフによる対応やプライバシーへの配慮を徹底し、安心して受診できる環境を整えています。
少しでも気になる症状があれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。