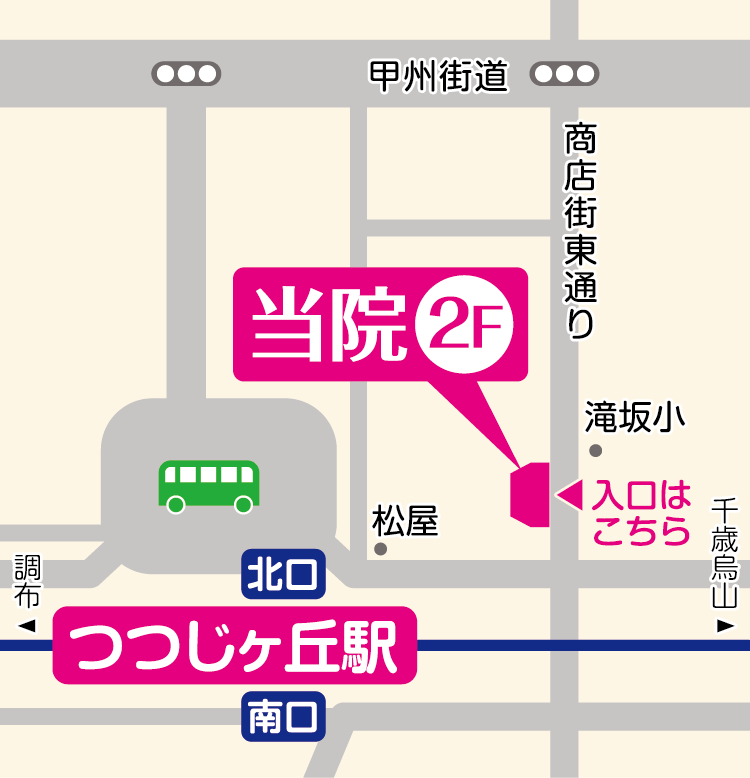尿路結石とは
尿路結石は、腎臓・尿管・膀胱・尿道といった尿の通り道(尿路)に石ができる病気です。
男性ではおおよそ7〜8人に1人(約12〜15%)が一生のうちに経験するとされ、女性では15〜20人に1人(約5〜7%)の割合です。男性は女性の約2〜3倍発症しやすく、特に男性は30〜50歳代、女性は50歳代以降に多くみられます。
一度できると再発しやすく、5~10年以内に約半数が再発するとされています。
結石は突然の強い腰背部痛(わき腹〜下腹部)や血尿を引き起こします。一方、小さな結石は無症状のこともあり、健診や超音波検査で偶然見つかる場合もあります。
このような症状があれば
ご相談ください
- 急に腰やわき腹が激しく痛くなった
- 血尿が出た
- 排尿時に痛みがある
- 過去に結石があり、再発が心配
- 健診で「尿路結石の疑い」と言われた
尿路結石の種類と位置
結石の成分・大きさ・できる場所によって症状や治療方針は異なります。
- 腎結石
- 腎臓内にとどまり、無症状のことも多い
- 尿管結石
- 腎臓から膀胱への細い管に詰まり、突然の激痛を起こすことが多い
- 膀胱結石
- 下腹部痛、尿のにごり、血尿、排尿障害を起こす
- 尿道結石
- 尿道内に結石が詰まり、突然の排尿痛と排尿困難を起こす
当院での診断と初期対応
当院では以下の検査で結石の診断・評価を行います。
- 超音波検査(エコー):結石の大きさ・位置、水腎症(尿の流れがせき止められている状態)の有無を確認
- レントゲン検査:結石の位置・大きさ・形を把握
- 尿検査・血液検査:尿路感染や腎機能障害の有無を確認
- 必要に応じてCT検査を近隣連携病院で行い、詳細を評価
治療方針
- 小さな結石(5mm以下)や症状が軽い場合
- 水分摂取、鎮痛薬、排石促進薬(α1遮断薬)で自然排石を促す
- 大きな結石(10mm以上)や痛みが強い場合、腎機能障害・感染を伴う場合
- 連携病院で体外衝撃波結石破砕術(ESWL)や内視鏡手術(TUL・PNL)を検討
明理会東京大和病院との連携
院長は休診日の木曜日に明理会東京大和病院で外来診療を行っています。
同院は尿路結石手術件数が全国的にも多い実績を有しており、ご希望に合わせ、ご紹介いたします。手術後のフォローアップは当院でも可能です。
再発予防にも力を入れています
尿路結石は再発率が高いため、当院では次のような予防策を行っています。
- 結石の成分分析に基づく食事・生活指導
(塩分制限・動物性タンパク制限・シュウ酸を多く含む食品の過剰摂取を控える・水分摂取 1.5〜2L/日) - 尿pH測定による酸性・アルカリ性バランスの評価
- 高尿酸血症・副甲状腺機能亢進症など背景疾患の評価
- 必要に応じた薬物療法(高尿酸血症の治療、尿アルカリ化など)
- レントゲンや超音波による定期的な経過観察(症状がなくても、半年〜1年ごとの検査で結石の有無や増大を確認し、早期対応につなげます
「痛くないから放置」は危険です
「痛くないから放っておく」ことは危険です。
無症状でも結石が尿の流れを妨げ、腎機能低下や感染症の原因になることがあります。
自然排石が見込めない場合や腎臓への負担が大きい場合は、早期治療が重要です。